MBAでは避けて通れない「グループワーク」。インターンでも企業が学生側にグループワークを課す場合が多いです。多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働することで学びは深まりますが、同時に価値観の違いから衝突が生じることもあります。今回は、私がインターン中に経験したチーム内の衝突と、その解決までのプロセスを振り返ってみたいと思います。
きっかけは小さな一言から
私のチームは3人。
- ロンドンから来た自信満々の学生
- アメリカ東海岸から来た聡明な女性
- そして私
最初は平和だったのですが、プレゼンの締め切りが近づいてくると、ロンドンの彼がイライラしはじめました。そんな時、女性が「そんなにナーバスになってもしょうがないよ」って一言。
彼女は場を和ませようとしたんだと思います。でも彼はこう反応しました。
「君はフルタイムのオファーを取る必要ないから、そんな軽く考えられるんだろ」
「俺は本気でオファーを取りに行ってるんだ。ヘラヘラされたら腹立つんだよ」
内心では「いやいや、二人とも直前まで大して進めてなかったじゃん…」とツッコミたい気持ちもありましたが(笑)、その場ではとにかく場を落ち着けようと必死でした。
衝突の裏にあったもの
冷静に考えると、この衝突にはいくつか要因がありました。
- モチベーションの違い
- 最終プレゼンと完璧に仕上げたいという学生と、グループワークよりも日常的に個人でアサインされるタスクを優先したいという学生の温度感の差。そして、フルタイムオファーを本気で狙っている学生と、まだ業界のお試しくらいのレベル感でとりあえずインターンに挑んでいる学生の温度差。
- 本番へのスタンス
- 「リラックスして臨みたい派」と「ピリッと緊張感を持って臨みたい派」の違い。「リラックスして臨みたい派」である東海岸の女性は、これまでの経験上緊張下でのプレゼンテーションがうまくいったためしがないし、少しフランクなくらいのプレゼンテーションの方が審査員のハートをつかめるしいいのでは?という意見。一方でロンドンの学生は、あえて緊張感を保つことで、最後までアイデアを絞り出せるし、小さなミスも発見しようというモチベーションにつながる、だからあえて自分を追い込む方がいいんだ、という主張。
- 情報の非対称性
- 学生間でよく話題になっていたのが、実際にフルタイムのオファーをもらえるかどうかは、いったいどんな基準に沿って判断されているのかということ。中にはインターン経験者で今社員である人たちに聞いて回って、どうやら最終プレゼンの結果はそこまで重要じゃないらしいと噂話をしている学生もいました。私の考えでは、学生側がその評価基準を完全に把握することは不可能であるし、たとえ判断基準をある程度知れたとしても(たとえばチームワーク適正、個人のハードスキル等)、そのスキルたちをどの時点でどのように評価されるかは運による部分も大きいと思う。つまり、インターン生という立場である以上、すべてのタスクに対して全力で挑むしかない、という理解である。
とった解決策
最終的に私たちが選んだのは、**「担当制をやめて、全員でスライドを一から一緒に確認する」**という方法でした。
- 担当制だと「この人にこの部分を任せていいのか?」という疑心暗鬼が生まれる。
- 自分の担当パートを勝手に直されると余計に不信感が強くなる。
だから時間はかかっても、みんなで1ページずつ見直し、修正点を「ここをこう直す、その担当は誰」と明確に決めて進めました。すると少しずつ信頼が戻ってきて、最終的にはチームとしてなんとかゴールできました。
経験から学んだこと
今回の学びはシンプルで、効率より信頼を優先した方が結局うまくいくということ。効率を追い求めても信頼が壊れると逆に非効率になる。一方で、多少時間がかかっても「一緒に作るプロセス」を共有すれば、不思議とチームはまとまる。
MBAやインターンでは「成果物」ももちろん大事ですが、それ以上に「人との関わり方」から得られる学びの方が大きいと感じました。
グループワークでの衝突って、正直どこでも起こります。でも、その過程をどう解決したかが自分にとって大きな財産になるんだと思います。
参考までに、MBAのグループワークがどういうもの何かについては、この方のブログが大変参考になると思いますので、貼っておきます。
https://japanmichiganross.hatenablog.com/entry/2021/01/27/052912
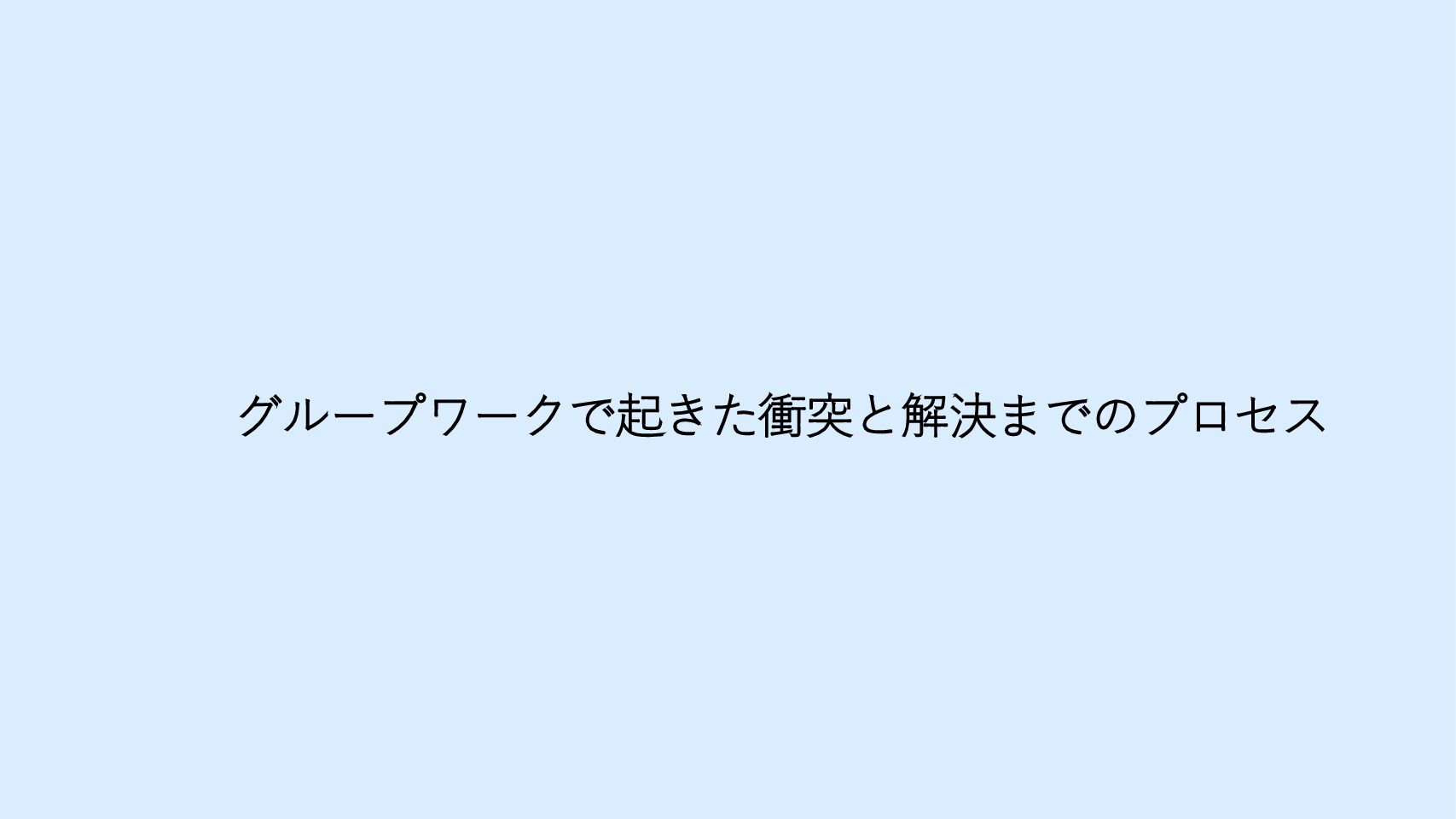
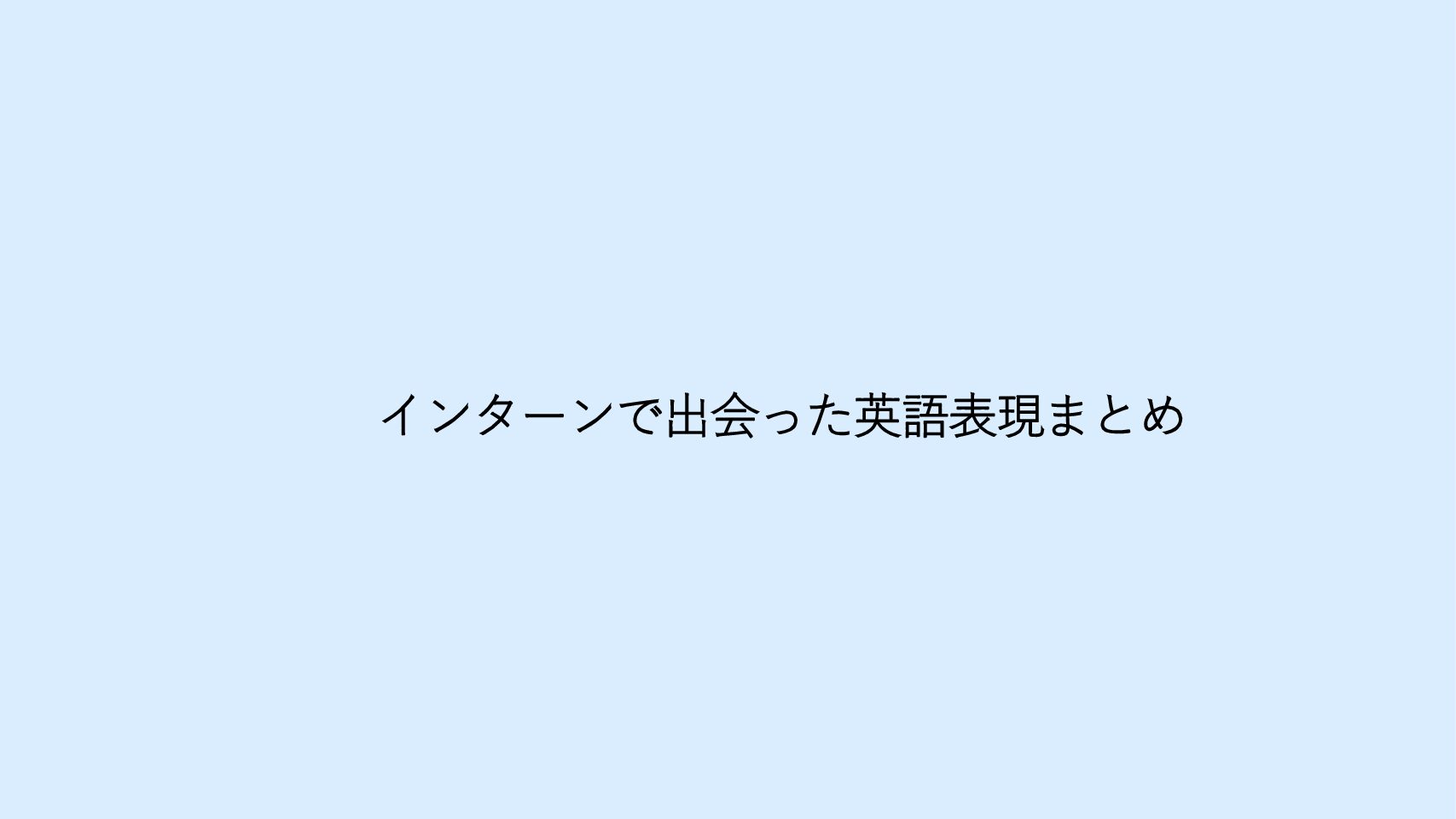
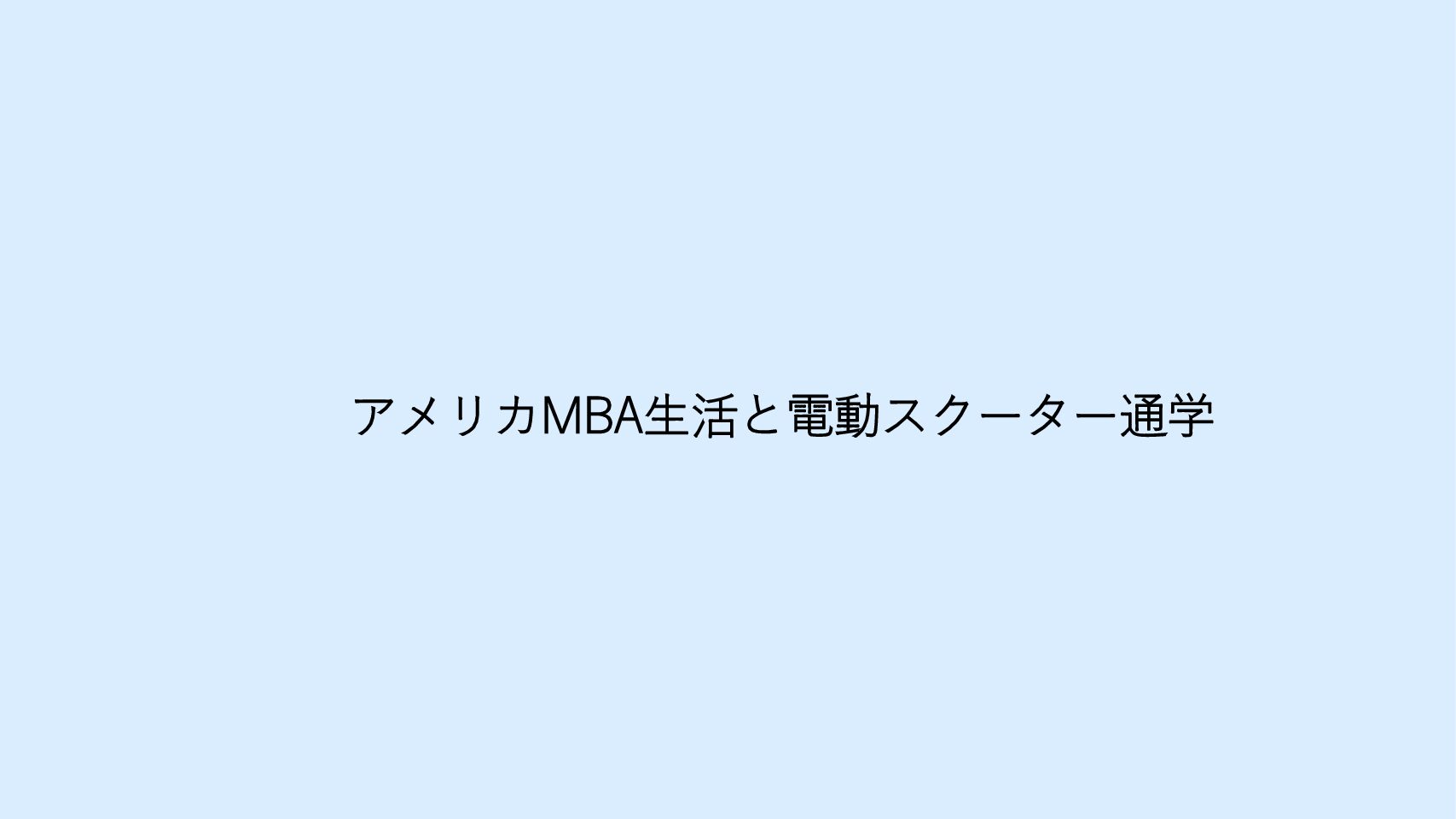
コメント