2025年の目標として毎月英語の本、日本語の本を一冊ずつ読むことを掲げました。今月は日本語の本として「対馬の海に沈む」というJAで起きた不祥事を題材にしたノンフィクションです。もともと2024年にノンフィクションの本を読むのにはまっていたのですが、この本がノンフィクションの賞を受賞したことをしって気になっていました。
あらすじは以下になります。
人口わずか3万人の長崎県の離島で、日本一の実績を誇り「JAの神様」と呼ばれた男が、自らが運転する車で海に転落し溺死した。44歳という若さだった。彼には巨額の横領の疑いがあったが、果たしてこれは彼一人の悪事だったのか………? 職員の不可解な死をきっかけに、営業ノルマというJAの構造上の問題と、「金」をめぐる人間模様をえぐりだした、衝撃のノンフィクション。
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-781761-4
この本をちょうど読んでいるときに、MBAの授業でOrganization Behaviorという授業を受けていました。簡単に言えば、どのような組織づくりをしていくべきかという点を深堀していくような授業です。今回の「対馬の海に沈む」の内容がすこしこの授業とリンクする部分があるように思えたので、ブログに残してみようと思います。
従業員のインセンティブ設計
企業のマネジメントとして、いかに従業員がモチベーション高く自ら与えられた仕事を高いクオリティで遂行していってくれるような組織を作れるか、というのは大きなテーマだと思います。ぱっと思いつきやすいのは、例えばボーナスを高くするとか基本給を上げるとか。あとは有給消化をしやすい環境にするとか、フレックスな働き方を許容するというのもよく耳にするものかもしれません。
インセンティブ設計は大きく分けて2つに分類されます。一つはExtrinsic motivation, もう一つはIntrinsic motivationです。日本語にすれば、外的要因と外的要因といったところでしょうか。
先ほどあげた基本給やボーナスを高くするというのはExtrinsicに該当します。”お金を稼ぐ”という外的要因をモチベーションに一生懸命働くという構図です。例えば、自分のノルマ次第で年末にもらえるボーナスが100万にも1000万にも、場合によっては1億もらえるとなれば、その会社の従業員は一生懸命働くように思えますよね。しかしながら、このExtrisic motivationにも弱点があります。それはCostと正当性です。給料をあげるとかボーナスを上げるという話は、企業からすれば従業員コストが増加することを意味しますよね。たとえ一人当たり数千円のベースアップだとしても、何万人と抱える大企業の場合それだけで財務に与えるインパクトは甚大です。もうひとつの弱点は正当性になります。これは実際授業のケースである小売店の事例がでてきたのですが、業績に応じて(例えばノルマの達成/未達成)ボーナスの額を増やすという制度設計にした場合、当然企業の狙いとしてはノルマ達成に向けて正当に努力してもらうということなのですが、従業員もそんなに単純ではありません。楽して稼ぎたいという欲求は誰でも、どこにでも落ちています。ケースで扱った小売店の場合は、従業員の不正が横行し、ノルマの不正申告や他人の売上を自分の手柄として報告するなど、職場環境は最悪になってしまいました。
一方でIntrinsic motivationはどうでしょうか。これは例えば”やりがい”や”企業文化”に触発されて、自発的にモチベーションを高めてくれるような要素を指します。企業側から具体的な人参(先の例ではお金)をぶら下げる必要がないため、内的要因として解釈されます。例えば日本の教職員について考えてみましょう。労働時間、プレッシャー、精神的に未熟ない子供に日々接するというストレスに鑑みて、お世辞にも職能に見合った高い給与をもらっているとは言えないと思います。そうであっても、教員を目指す人は私の大学の同期にもいましたし、私がこれまで接してきた先生はどれも素晴らしい人々でした。これは、給与以外に「子供の成長を支援すること」などにやりがいを覚えているからではないでしょうか。
制度設計の難しさ
ここまで読んでいくと、じゃあ企業にとってコストもかからないし、職場の雰囲気や社員の士気が良くなるIntrinsiv motivationをうまく組織に発生するようにすればいいじゃないかと思うかもしれませんが、やはりこちらもそうは簡単にいきません。Intrinsic motivationを発生させるには、企業文化や哲学を浸透させる必要があります。でも企業文化を組織に広めるにはどうすればいいのでしょうか?以外と思いつかないのではないでしょうか。例えば私の前職は企業全体で300人、本社以外の支店はなく、基本的には全ての社員が同じ建物で働いていました。それでも、企業のスローガンやマネージング層の想いへの反応の仕方はさまざまでした。ある人は会社をよく思い、ある人はすべての会社の決定に愚痴を言ってたりしてました。たった300人の組織ですら、人の感情のバラエティ具合はすごかったので、支店があったり、もっと部署が多数にわたっている企業が一つの企業文化を意図的に根付かせるなんてことはよほど骨が折れる作業だと思います。また、Extrinsic motivationよりも、効果があらわれるまでの時間がどのくらい必要かも読めません。
JAの不祥事の場合
「対馬の海に沈む」で書かれる不祥事はまさしくExtrinsic motivationの制度設計の不備が、社員の不正を進める方向に働いてしまっています。本によると過度なノルマ設定によって普通に働いているだけでは達成はほぼ不可能というノルマだったそうです。またノルマ達成をした従業員への見返り・報酬は度を過ぎています。あらすじ記載のとおり、内外から神様扱いされ、会社のお金で海外慰安旅行にも行けたそうです。逆にノルマ未達の社員は必要以上に冷遇されています。そうすると従業員としては不正をしてでもノルマ達成という状態にしておきたいと考えます。そして一度不正を働いてノルマ達成してしまうと、その甘い蜜と周りからのさらなる期待、そして不正を働いていることに対するストレス発散のための散財、と負のスパイラルから抜けられなくなります。
ここから見えてくるのは、やはり企業のモチベーション設計の大切さです。企業は利益を出すことが大事ですが、制度設計を誤れば不正を助長してしまうような環境を作ってしまいます。JAのケースに至っては、社員一人の命がなくなるまでにことが至ってしまっています。
まとめ
勝つMBAで受けている授業は意図していないところである点とつながったりします。最近久しぶりにconnecting the dotsというフレーズを聞きましたが、まさしくそんな感じです。今までOrganizaation Behaviorは正直つまらない科目でしかも朝の8時から開始なのでモチベーションが低下していたのですが、この本を読んでから授業が楽しみになってきました。まさしくIntrinsicですね(笑)
以前書いた別の書評も読んでいただけると嬉しいです!
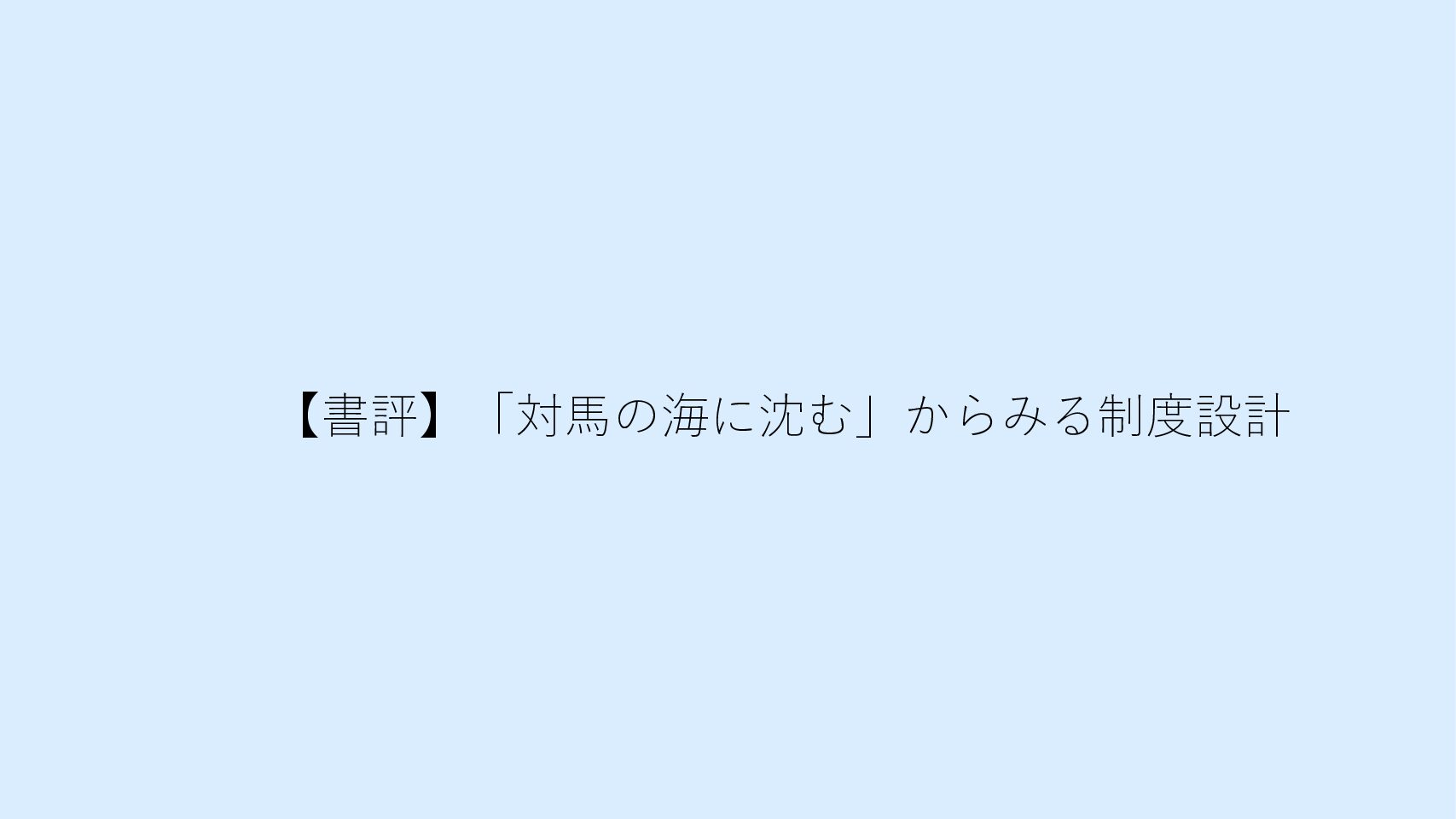

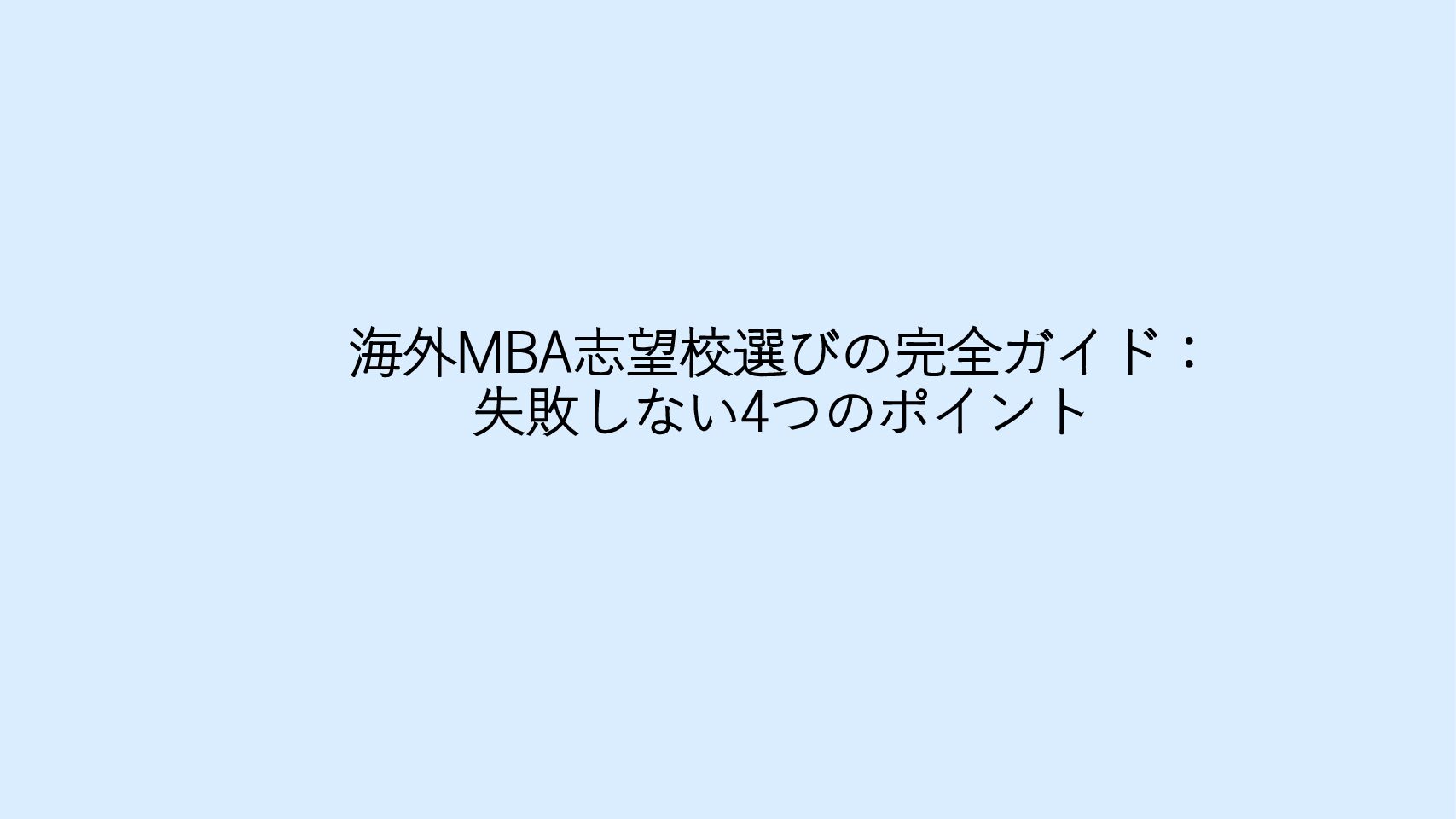
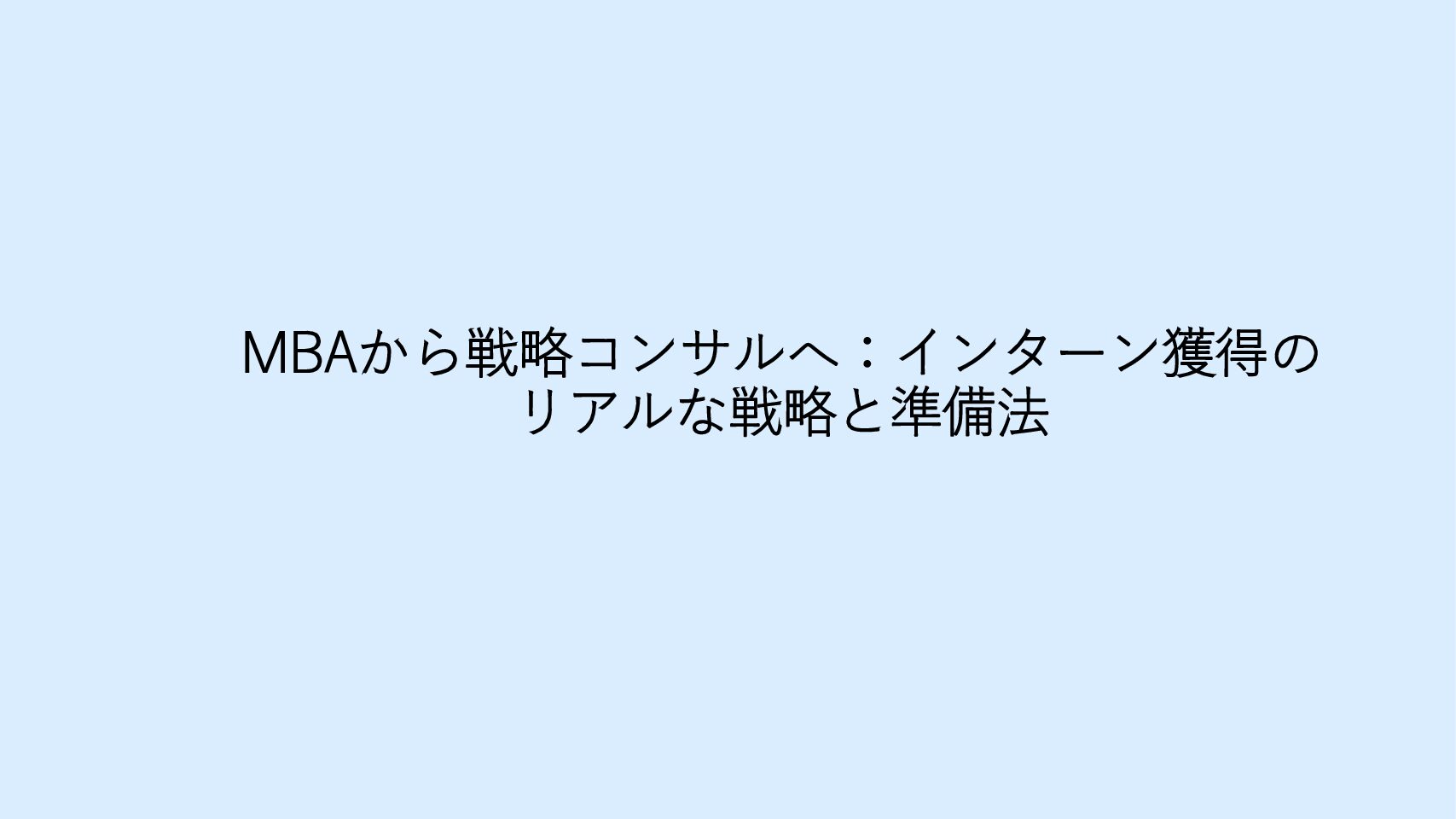
コメント