私が受験生だったとき、正直言って受験校についてあまり深く考えていませんでした。というのも、純ジャパで、そもそも海外での長期生活経験がなかったため、米国、ヨーロッパ、アジアのどの地域も一様に魅力的に感じる一方で、同じようにどの地域にも不安を抱いていました。その結果、漠然とした気持ちしか持てず、具体的な方向性を見いだせない状態でした。
また、いわゆるMBAランキングの表を眺めても、「そもそも英語やGMATのスコアメイクがまだ完了していないし、自分が出願できる学校なんて存在するのだろうか?」と思ってしまい、どうしても自分事として捉えることができませんでした。ただランキング表に表示されている学校を見つめて終わる、という状態が続いていました。
そのような状況でスコアメイクが完了した段階に入っても、各学校の情報を真剣に収集することができておらず、コーヒーチャットや説明会に参加する機会も有効活用できていませんでした。結果的に、進学先の学校の選択は自分のキャリアにとって良い選択だったと思えていますが、それは偶然運が良かっただけだったと言えるでしょう。
現在、米国MBAに通い、実際に海外で生活したり、リクルーティング活動を行ったり、学校がどのようなサポートを提供してくれるのかを身をもって経験しています。今振り返ると、「こういった視点で学校選びをしていれば、より効率的に志望校リストを作成できたし、情報収集やスコアメイク対策にももっと力を入れられたのではないか」と感じます。
そこで今回の記事では、私が考える志望校選びの際に重要な5つのポイントについて記載していこうと思います。
ランキング上位校にこだわるべき
日本企業に勤めていると、「海外MBA」というだけで「おお、すごいじゃん」といったリアクションをもらえることが多いと思います。しかし、その背景には、多くの人が海外の大学院の優劣について正直あまり詳しく理解していないのではないか、と感じます。
ハーバードやスタンフォードはもちろんすごいし、UCLAやUCバークレーも聞いたことがあるからすごそう。でも、INSEADは正直聞いたことがないな……というような感想を抱く年配の上司を持つ受験生も多いのではないでしょうか。
私自身もMBAに実際に来るまで、正直MBAランキングがどれほど重要なのかよく分かっていませんでした。「このランキングに入っている時点で、各国のスーパーエリートたちが集まっているのだから、どこでもすごいってことじゃないの?」という感想を抱いていました。
MBAのランキングというと、代表的なのは2つほどあります。
一つ目はFTが出しているもの、二つ目はQSから出ているもの。これ以外にも、ランキング形式で毎年発表している機関はいくつか存在します。ランキングの算出方法は各社で異なり、機関ごとに上位校の顔ぶれも変わることがあります。また、「この学校がこの順位はないだろう……」と思うようなケースを目にすることもあります。
というのも、MBAを評価する際にイメージしやすい指標としては、入学難易度、就職先、アルムナイのサラリーや影響力といったものがありますが、それ以外にもダイバーシティや、合格を出した生徒の中からその学校を進学先に選んだ割合といった要素を採点項目に含めている機関もあります。
そうなると、「ランキングって本当に意味があるの?」という疑問が湧くかもしれません。しかし、そんなことはありません。確かに、数年単位で見ればランキングの入れ替わりは激しいですが、10年、20年といった長期的なスパンで見ると、常にトップ10やトップ20にランクインし続けている学校が存在します。
こうした学校は歴史や伝統があり、例えば米国では「M7」といったカテゴリーに含まれるような名門校です。ランキングのスコアリング方法に多少の疑義があるとしても、大手のランキングで安定して上位にランクインしている学校は、生徒、アルムナイ、企業から非常に高い評価を受けていることに間違いはありません。
では、なぜランキングが高い学校に入ることが大事なのでしょうか?それはシンプルに、ランキングが高い学校=プレゼンスが高いからです。
海外MBAには試験一発勝負という形式がなく、日本の大学のような偏差値表も存在しません。その代わりとなるのが、このランキング表です。つまり、東大や京大がある中で、早慶をあえて目指す人がごく少数であるように、多くの人は第一志望の学校に落ちてしまった、あるいは試験科目数や難易度と自分の実力を考慮して志望校のレベルを少し下げる、というプロセスを経て早慶やその他の学校を選ぶことが多いのではないでしょうか。このような志向プロセスは海外でも同様です。
「なぜハーバードでないの?」「なぜスタンフォードでないの?」という質問には、明確かつ合理的な理由が必要です。例えば「超ニッチな産業にキャリア志向があり、その産業ではA大学が最もプレゼンスが高い」といった理由があれば納得されますが、そうでない場合はGMATやエッセイ、インタビューのいずれかのプロセスでトップ校に入る実力が不足していたのだろう、と見られてしまいます。この視点は特に、海外MBAを卒業後に現地での就職を目指す場合には非常に影響が大きいです。
そのため、特に明確な理由がない場合は、とにかくランキング表で1つでも上位に位置する学校を目指すことが重要です。
ロケーションは超重要
正直ロケーションなんてどこも住めば都だろうと思っていましたが、留学して気づいたことの一つは、実はキャンパスのロケーションがどこにあるかは非常に重要だということです。
ひとつには、就職活動です。日本の学部卒の就職活動をイメージしてみてください。旧帝大は早慶上智と同等あるいはそれ以上に評価の高い大学郡だと思います。しかしながら、早慶上智はキャンパスが東京にあるという利点から、相当アドバンテージを享受していると思っています。合同説明会、企業訪問、OB訪問、インターン、どの観点からもやはり都心に住んでいるというロケーションのメリットは計り知れません。これと同じ現象がMBAでも起こります。例えば、アジア(具体的にはシンガポールや香港)での現地就職を考えているとき、わざわざロケーションの遠いヨーロッパの学校に入学するメリットはほぼないでしょう(ハーバードなど米国の超トップ校であれば話は別です)。また、米国においても、もし金融業界(投資銀行やPE)に就職したいのであれば、やはりウォール街に近い東海岸の学校を狙った方が良いです。例えば、私の場合西海岸の学校ですが、Tech系やVC系の企業へのアクセスは抜群にいいですが、投資銀行(かつNY支店)を目指している学生が、面接の度にNYに呼ばれており、相当大変そうです。ちなみに、東海岸と西海岸では飛行機で6時間ほどかかるうえに、時差もあります。
またもう一つロケーションの観点で大事なのが、家族の生活です。もしあなたがパートナーや子供を連れた留学となる場合には、ロケーションはやはり大切です。独り身であれば田舎の学校ですべての学生が寮に住むような場所でも楽しくやっていけるでしょうが、家族がいる場合には学校やパートナーの生活のケアも大切です。その場合、やはり商業施設、教育機関、小回りの利く交通機関、日本人コミュニティの充実といった観点から、自然と都心に位置する学校がよいと言わざるを得ません。もしパートナーが仕事を辞めて帯同してくれる場合、日中時間を消費できる場所(美術館でもカフェでも映画でも語学学校でも)があるだけで、パートナーの満足度はかなり変わります。MBA生本人は、授業の予習復習、グループ課題、就活、ソーシャル活動と授業以外でも何かと時間を奪われるので、平日はほとんど家族とゆっくり過ごすことができません。その点で、やはり本人だけでなく、家族から見た視点で学校周囲の生活環境を考慮に入れる必要があるでしょう。たまに聞きますが、家族が生活環境に嫌気がさして家の雰囲気が最悪、、、とか日本に変えるとか、あるいはもっとメンタル的に厳しい状況に陥ってしまったとかいうケースがあります。当然家族の調子が悪ければ、本人の調子も万全とはいかず、苦労して手に入れた夢のMBA生活を思う存分楽しむことができなくなってしまいます。
学費(奨学金)
MBAに入学する前は、正直どこの学校に行っても学費が高額になるのは変わりないのだから、別に気にしなくてよいだろう(どうせ資金繰りは苦労するだろう)と思っていました。しかし、実際に入学してより現実的に卒業後の生活をシミュレーションすると、結構厳しい状況に直面します。単純に1年制プログラムと2年制プログラムでは、かかる金額は2倍以上になります。特に米国の学校に入学するのであれば、家賃(いくら学校の寮に入れても)、水光熱費、食費は想像を超える重荷になってきます。
そのような状況のもと、MBA卒業後の進路をどうしようかと考えると、やりたいことやこれまでのキャリアなどは一度脇に置いて、やはり借金をできるだけ早く返せる仕事につかなくては、という思考になります。つまり、投資銀行、戦略コンサル、PEといった激務高給界隈です。うまくいくかわからない起業やスタートアップのストックオプションで一攫千金!みたいな悠長なことは言っていられません。とはいえ、IB、戦コン、PEの入社難易度はかなり高いので、希望通り入社できるかはまた別の問題です。
仮に入社できる能力が備わっていたとして、もしあなたのキャリアビジョンが明確に他の業界・分野にあるのだとしたら、資金面の問題から数年全く関係のない業界を挟み、遠回りをしなければいけない状況について、MBAに来てよかったと思えるでしょうか。そのくらい卒業後の資金繰りをきちんと計画しておくのは重要なことです。また上述の理由から、奨学金の獲得額によって志望順位を変えるというのも十分理にかなった判断だと思います。学校によっては日本人のアルムナイが立ててくれた奨学金財団や、学校から返済不要の奨学金を取得できるチャンスを提供してくれるものもあります。コーヒーチャット等でそのあたりの情報をきちんと聞いておくことをお勧めします。
特定業界に関する授業
MBAの授業なんてどこも同じことをやってるわけでしょ?という批判は一部正しく、一部は間違いです。確かにコアクラスと呼ばれる必修授業は大方どこの大学でも扱う授業は一緒、かつ内容もハーバードのケースだと思うので、内容としては大差ないともいえると思います(授業のスタイルや成績の重み、学校のカルチャーによって授業の雰囲気や生徒のやる気はだいぶ変わってきます)。
一方で選択授業については各学校でかなり特色が出てくると思っています。例えば、総合大学を擁する学校は、MBA生であっても学部の授業を取得することができ、哲学や芸術など非常に広範囲な授業を受けることができるでしょう。
また、私が授業という観点から学校選びで強調したいのが、特定の産業に関する授業の評判です。例えばあなたがスポーツビジネスに興味があるとして、スポーツビジネスに関する授業が充実しているかどうかはチェックする必要があるでしょう。それはもちろん授業の内容でどのようなことを吸収できるかも大事ですが、特にこうしたニッチ産業については世界が狭く、教授のコネクションがかなり効いてきます。授業で熱心にアピール教授との関係性を築くことができれば、エクスクルーシブな美味しい案件の紹介を受けることも可能です。実際に私の身の回りでも求人にでていないインターンを獲得できている生徒がいます。また卒業後もそうしたコミュニティに属していることは、これからのキャリアで大きな武器になるはずです。
まとめ
以上が私が入学してから感じた、学校選びで注意すべき項目になります。もちろん、他にもたくさん見るべき個所はありますが、少なくとも上記にあげた4点はシッカリ見たうえで志望校を絞っていかないと、後々後悔することになってしまうかもしれません。
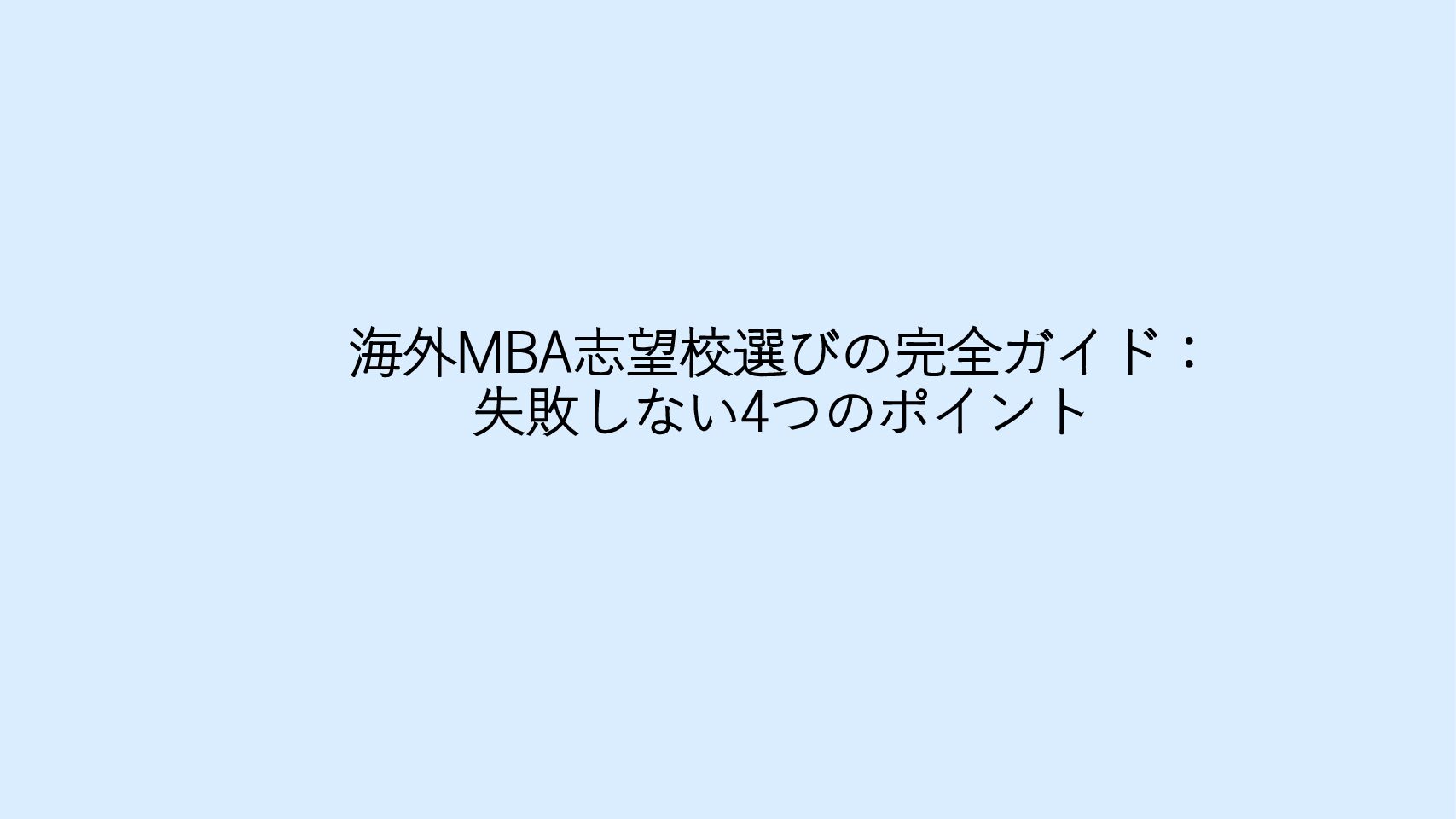
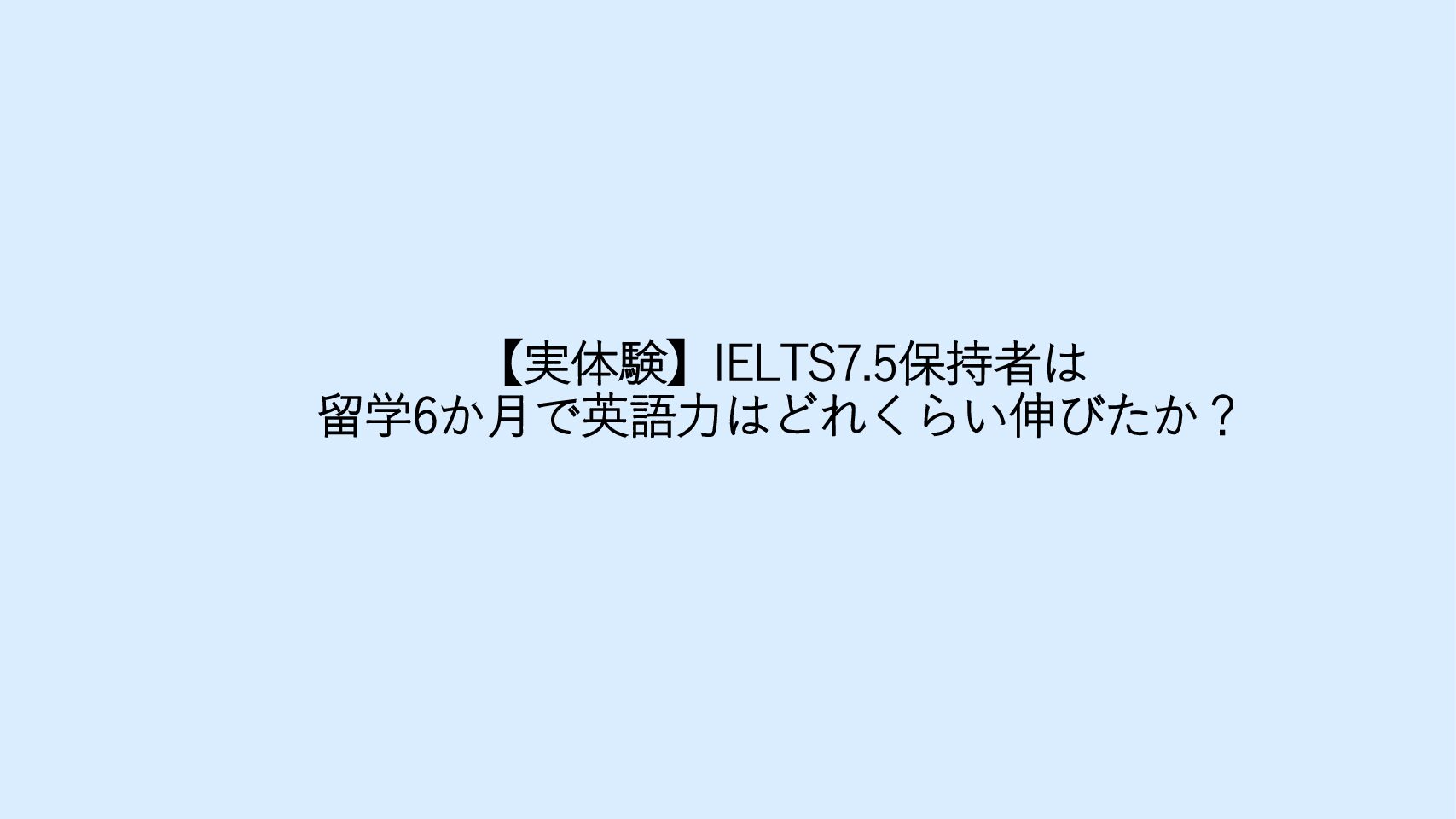
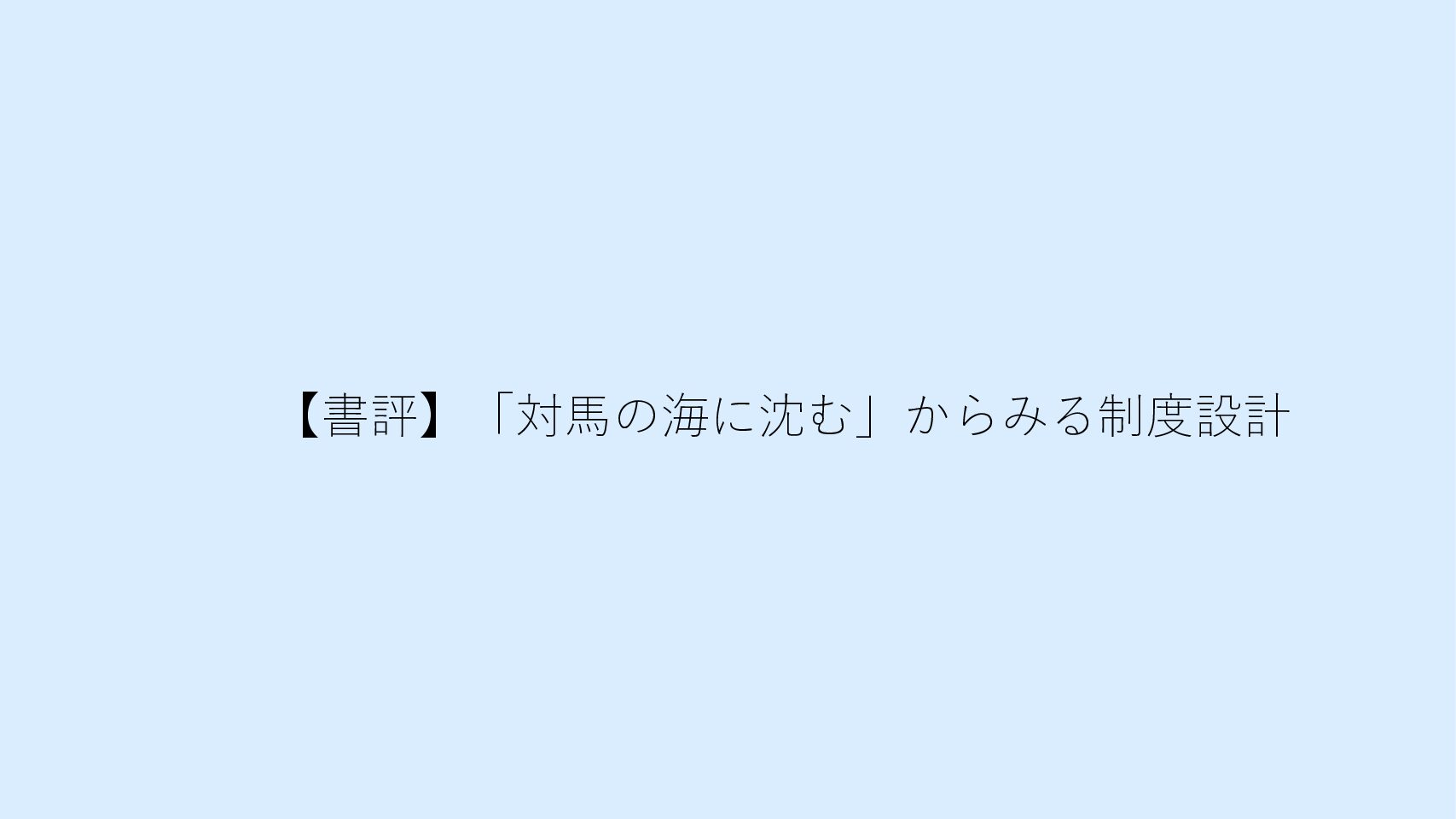
コメント